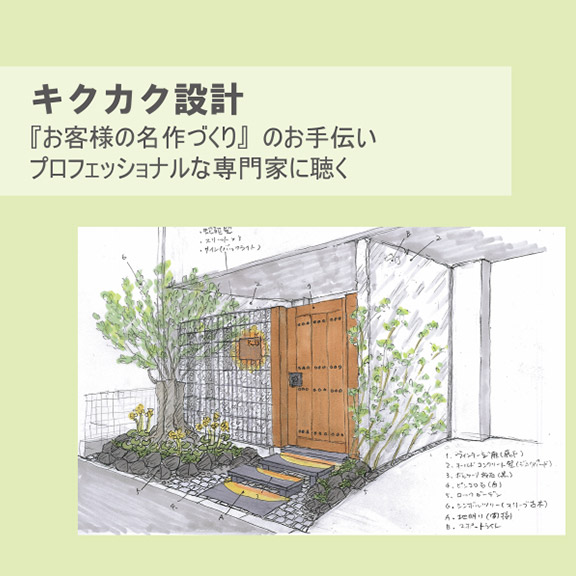CONCEPTS
 住宅一筋50年
住宅一筋50年
『自然素材で健康に暮らせる家』
私たちは、健康に暮らせる家を真剣に考えました。
その答えが、自然の力を最大限活用した自然素材の家です。
夏涼しく、冬温かいをあたりまえにするには技術と手間が必要です。
三重県でマイホームをお考えの皆さまへ
快適で、健康で、幸せな暮らしを
一緒に創っていきましょう。
LEARN MORE
志摩市・伊勢市・鳥羽市の注文住宅・移住住居・別荘・新築建築なら株式会社坂下工務店
プロの目線からご提案。伊勢市・松阪市・津市・志摩市の注文住宅・新築戸建てを手がける工務店なら当社へ。






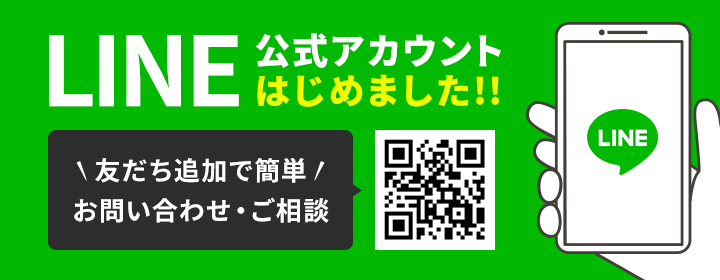


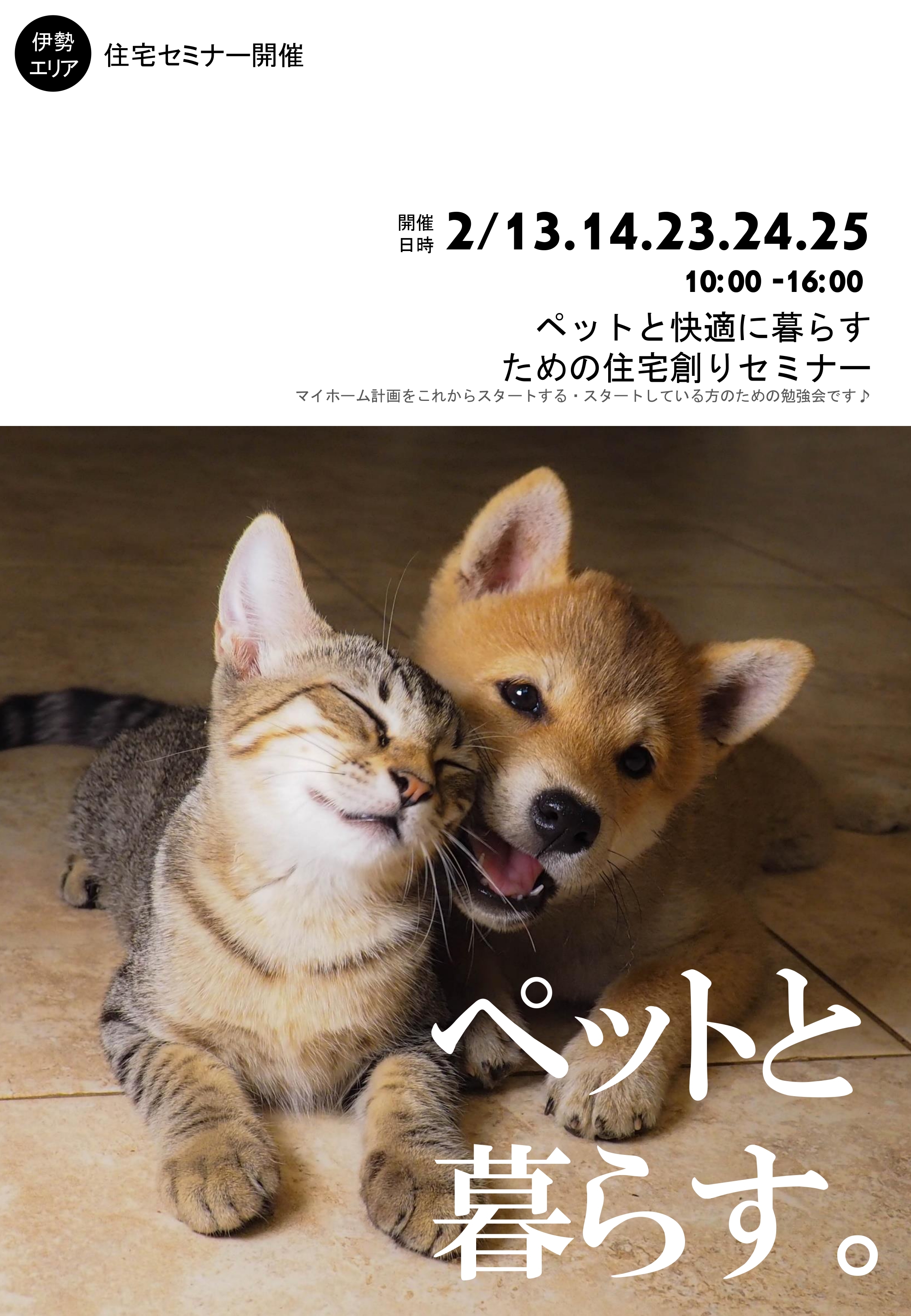
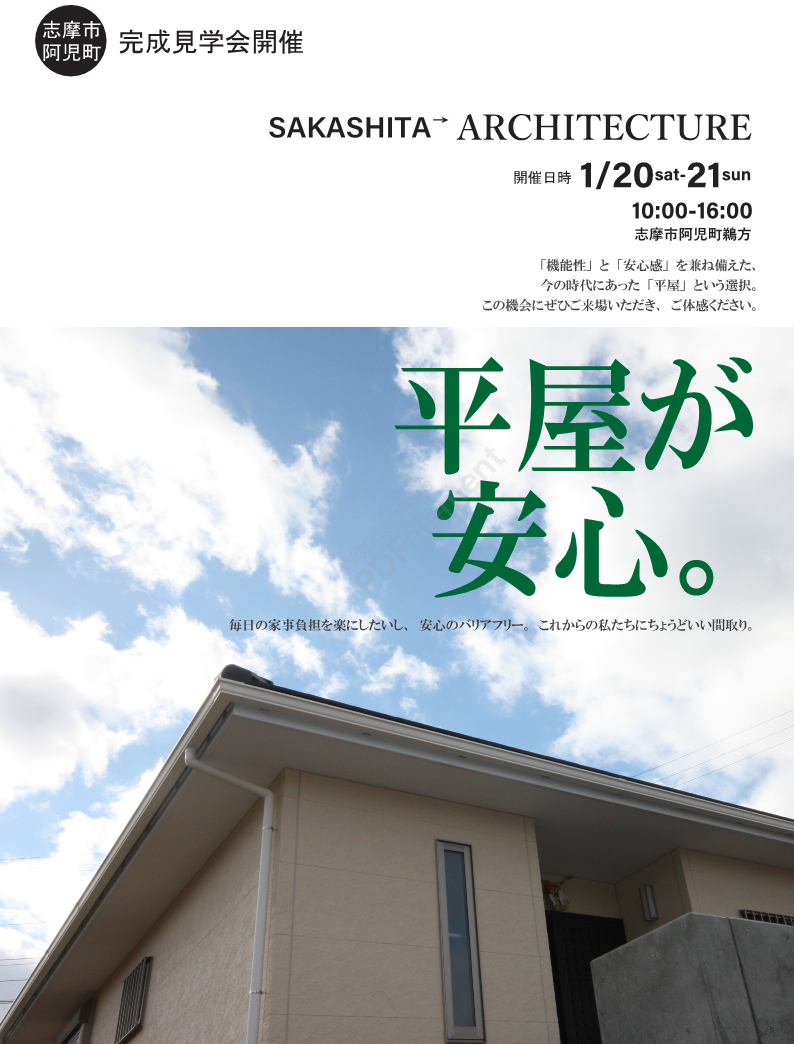
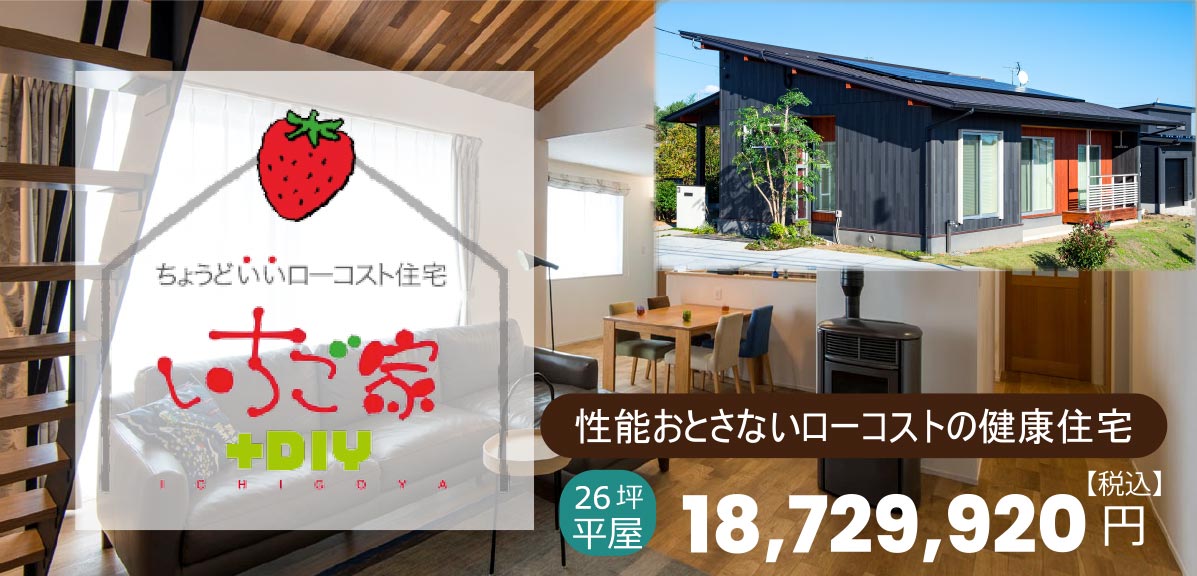

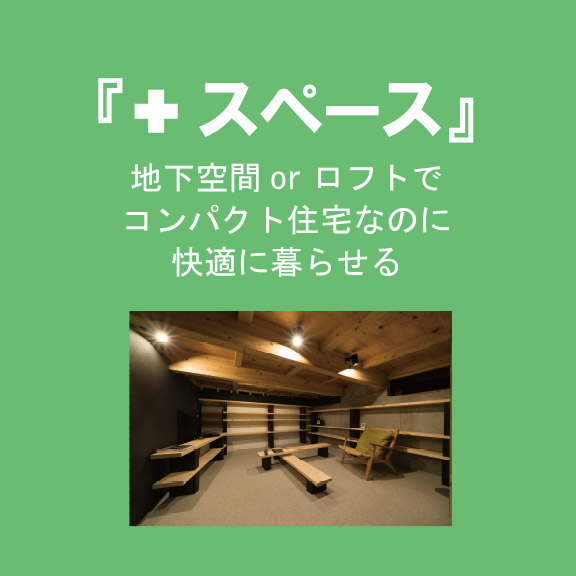



.jpg)







.jpg)



.jpg)